BLOG
ウォーキングブログ
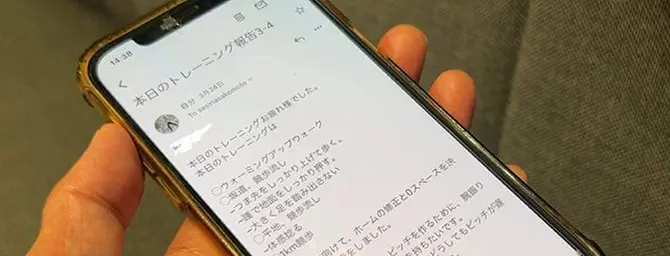






ウォークでも、ランでも、ウルトラ(100㎞以上)の大会で活きる、「耐乳酸性」と「脂肪優位」を向上させる方法

基本的なことを。
人が身体を動かすと「糖代謝:脂肪代謝」がされています。
脂肪は皮下脂肪や内臓脂肪として貯めることができ、
「糖」は筋肉内に貯めることが出来ますが、脂肪ほど体内に貯めておくことが出来ません。
「糖」をエネルギーとして燃やすと、「乳酸」が生み出されてしまい
乳酸自体は代謝物でもありますが、筋肉が硬くなる、いわゆる疲労を起こします。
ですから、この乳酸を生まないようにすることが、
長距離系種目ではとても大事なのです。
3年前にもブログで似たようなことを書いてます。
下に続きます。
小江戸大江戸200㎞のトップゴールの女性
24時間走(279㎞)の世界チャンピオンの男性
Twitterを読んでみました。
面白いことに2人とも別々のアプローチで
このウルトラマラソンに取り組んでます。
公務員で激務の中、10㎞くらいしか走れない方
しっかりとトレーニングをして、補給も工夫に工夫をしている方
まったく環境も違います。
ですが共通点もあります
「マラソン」で速いタイムを持っている
ということ。
女性は2時間45分に男性は2時間24分。
確かにマラソンのトップアスリートに比べれると見劣りはしますが
素晴らしいタイムです。
速いペースでも42㎞を走れる、というのは
・「耐乳酸性」に優れている。
・「脂肪優位」で走れいている
ということです。
これは、長時間のレースでも大きなアドバンテージです。
糖を燃やせても疲れにくく、糖を燃やすので血糖値スパイクが起きにくい「耐乳酸性」
糖をわずかに燃やし、脂肪をメインに燃やすことでエネルギー摂取で最低限の糖摂取で済むので
血糖値スパイクのリスクが低くなる「脂肪優位」
どちらも血糖値スパイクのリスクが低くなり、ウルトラでは向上させたい能力でしょう
では、この2つを鍛えるにはどうすれば良いでしょうか?
「スピード練習」はしたいですね、しっかりスピードを出せる距離
3㎞のインターバル、とかですね。
個人的には3㎞×10、とかまではありますが
100㎞を意識するなら3㎞×20とかしたいですね。
「耐乳酸性」はある程度、乳酸がでても動き続けるトレーニングです。
スピードを出して心拍数を上げて、糖代謝を優位にして乳酸が出る
その状態でどこまで粘れるか?距離が長すぎると潰れてしまいますが
潰れ切らない距離で一度ゴールし、補給し直して再度スタートする、を繰り返す
「脂肪優位」にして身体を動かせるようにするにも
スピード練習をして、最大心拍数を上げてLT値を上げていくことが大切です
これは、もっと距離を短くして高い心拍数を繰り返し作る
2㎞×25本、とかできれば良いですね。(これはかなりきつい。。。)
総合的にやるならば
3㎞×10+50㎞ウォーク、
3㎞でスピードを意識して、50㎞は最初から突っ込むような。
厳しいメニューですが、ウルトラのランの人はもっとすごいことしてます(苦笑)
しかも、食わずに走れば速い!とも言ってます
これは理屈に合ってるんですよね、糖を摂らないから乳酸が出ない
脂質代謝だけで走るので理論的には体脂肪が無くなるまで走れる(笑)
ウォークにせよ、ランにせよ、スピード練習をするのは
ウルトラの能力を上げることにもつながるでしょう









